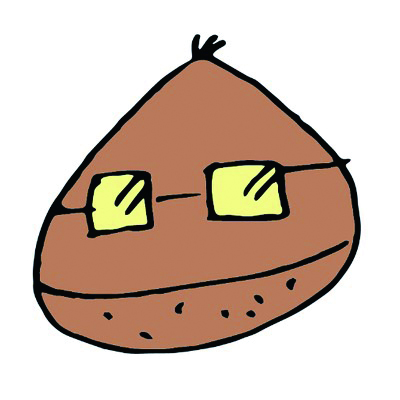
批評家。『LOCUST』編集部。京都演劇ガイドブック『とまる。』(2008~2012 年) を創刊・発行。「チェルフィッチュ(ズ)の系譜学――新しい〈群れ〉について」(『ゲンロン 9』 2018 年 10 月号)でゲンロン佐々木敦批評再生塾第三期最優秀賞を受賞。論考に「「わたしたち」 の健忘症、あるいはエクソフォニーが開く〈夢の脈絡〉」(『多和田葉子/ハイナー・ミュラー 演劇表象の現場』、東京外国語大学出版会、2020 年)、「観(光)客はいかにして場違いな O に犯さ れるか―したための『文字移植』を/から再読する」(『多和田葉子の〈演劇〉を読む――切り拓 かれる未踏の地平』、論創社、2020年)、「ポストシアターの加速――COVID -19にF/Tはいか に応答したか」(「悲劇喜劇」2021 年 1 月号)等がある。
秘密結社――R3:Scape-Cityにおける〈秘匿〉の身振り
渋革まろん
立川駅で乗り換え、中央線特急に乗って1時間半ほど。眠たい目をこすりながら到着したのは下諏訪駅。あずさ、養老乃瀧、本山川魚店……ぽつぽつと点在する飲食店が土地の空気を醸し出している。というより、よく馴染むと言ったほうがいいか。盆地特有の、まわりをぐるりと山に囲まれていることによる安心感を感じながらとぼとぼと歩いていると、遠くから微かにシューベルト「アヴェ・マリア」のハミングが聞こえてくる。え、なにここ? そんなことってある?
2021年6月25日からの3日間――アーティストの滞在は23日からだったようだ――長野県の諏訪盆地地域に滞在した私は、パフォーマンスアートフェスティバルを通じた国際シンポジウム「Responding」の参加アーティストに混ざって、その活動の一端を体験した。2018年から毎年開催されているRespondingは、各国地域で活動するパフォーマンスアーティストのネットワークを基盤として「社会が直面する困難な課題に対して多角的な視点から新たな光を当てる」インターカルチュラルなパフォーマンスプロジェクトである。2020年にはシンガポールのアーティスツ・ビレッジとの共催で諏訪地域にて、2021年にはシンガポールにて開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響で延期になり、2021年は原則非公開で、参加アーティストのパフォーマンスを映像作品あるいは記録として現地にて収録することになったようだった。
さて、「ようだった」という距離が示すように、私はRespondingの活動の全体をあまりよく知らない。RespondingのWEBページでは、アーティストが地域の「部外者」であり「異邦人」であることが強調されているが、私はいわば「部外者」の「部外者」、「異邦人」の「異邦人」という立ち位置にいた。だから、本プロジェクトを総括するようなことは何も言えない。しかしそれゆえに、“何”であるのかよくわからないものに触れていくような、新鮮な驚きを持って本プロジェクトを経験した。実際、3日間の滞在期間を経て、私の口からはある言葉が不意に飛び出してきたのだった。この人達、なんだか秘密結社みたいだな――。
そこで本稿では、ひとつひとつのパフォーマンスから引き出された体感的な手触り、この“旅”の過程が「私」という身体の結節点にいかなる経験のふくらみをもたらしたかを語り直すことを試行する。最後にRespondingに感じ取られた「秘密結社」をひとつの「応答」として受け止めるための仮設的な視座を提起してみたい。
DAY1 旧御射山
1-1 身元不明の聖火ランナー

Respoding:3(以下、R3)のステイトメントでは、「Scape City」というコンセプトが打ち出されている。
「Scape-City」とは、諏訪盆地地域の文化圏「スワニミズム」を基点として、避暑地という言葉にあるような都市部からのエスケープに留まらない、現代社会に於ける「都市のあり方」を複層的な「Scape」として見直す試みである。[i]
第一に諏訪盆地地域の「スワニミズム」という文化圏に、支配的な社会空間から逃走(escape)=離脱する祝祭空間としての可能性を見出す。第二に陸上交通の要地として栄えた諏訪地域を「複数文化の交差路」と解釈して、複層的な景(Scape)が折り畳まれた都市のあり方を探る。第三に脱-社会的な諸個人の協働による多種多様なパフォーマンスから文化的な共生のあり方を探求する。そして第四に多様な文化・都市・コミュニティの結節点となる新たな芸術表現の可能性を探る。
先述したとおり、もともとの計画ではシンガポール・諏訪という対称的な二都市に通底する課題―応答を模索することから、東京一極集中と地域産業の空洞化が表徴するような、国境を横断して非領土的な政治経済的ネットワークを広げていくグローバル資本主義の諸課題に応答することが構想されていた。しかし、さしあたり2021年のR3では諏訪というローカルな地理的・歴史的文脈に根ざした文化研究・コミュニティ形成・芸術実践という相互連関する3つのフレームが設定されている。それらのフレームを通じて、諏訪文化圏に既存の社会秩序から脱去する――諏訪地域と他のコミュニティの双方にとっての――「外」を見出し、文化の境界を再定義するパフォーマンスの祝祭空間を出現させ、このような仕方で複数文化の交差路=共働的コミュニティを構想するとまとめられるだろうか。[ii]
R3の参加者はトロント・東京を拠点とするアーティストでありResponding総合ディレクターを務める武谷大介をはじめ、パフォーマンスアーティストのたくみちゃん、前田穣、村田峰紀、濵田明李、そして研究者の瀬藤朋、牧田義也の計7名。そこに私がちょこんと参列した。滞在した3日間の様子を概観しながら、いくつかのパフォーマンスにコメントを加えていこう。
1日目、つまり6月25日。このあとのパフォーマンスで使用する予定だという器を購入するため、宿近所の古道具屋に立ち寄るとのことだったが、本日休店との情報が入り、はやくもなにか不穏な暗雲が立ち込める。スケジュールは詰まっている。時間がない。ほとほと困っている様子の牧田さん。後で聞いた話によると、今回のレジデンスでは組織的な役割分担がなされているわけではなく、牧田さんが自発的にスケジュール管理全般を引き受けているらしい。
立ち往生する一行だったが、宿のスタッフの方からリビセンだったら開いてるかもとの有力情報が提供される。「おぉ、そうだ、リビセンがあった」――リビセン、すなわちリビルディングセンタージャパンとは、上諏訪地域にある有名なリサイクルショップである。[iii]「あそこはなんでもあるからね、良い器があるよ」ということで、一同、車に乗り込みリビセンへ。レトロ食器、徳利、お茶碗、小引き出し、木っ端に鉄瓶、謎の医療器具など夜な夜な付喪神の饗宴が開かれていてもまったく不思議でないほど多種多様な小道具が並ぶ棚から、各々の感性にフィットする器を入手する。
のち、一行は八島湿原を抜けたところにある旧御射山(もとみさやま)遺跡に向かった。旧御射山は諏訪信仰の要地であり、江戸時代初期まで諏訪神社下社の御射山祭が開かれていた。[iv] 牧田によれば、旧御射山遺跡は「古代のオリンピック」が開かれた「日本最古の競技場」と言われており、鎌倉時代には諸国の武将を集めた大規模な祭りが実施されていたという。
現地は広大な野原になっていて、四方に御柱が建てられた小さな祠の前からは、湧き水が溢れ出している。そこから流れる小川を挟んで向こう側に、草緑に覆われて小山のようになった階段状の遺跡がある。鎌倉時代には、あの段々に座り、神前に奉納される流鏑馬の儀式を見ていたのだろうか。そんなことを思っているあいだに、カメラのセッティングは着々と進み、前日のミーティングで決まったという「水のリレー」が行われた。小川が湧き出る水源のあたりから、その小川で汲んだ水を器から器へとリレーしていこうという構想だ。こうして聖火リレーになぞらえられた「水のリレー」は東京まで運ばれていく……。それは当時開催まで1ヶ月を切っていた東京オリンピックにおける聖火リレーとの対比を否が応でも想像させる。
ただ、平和のシンボルとしての聖火リレーは古代ギリシャの時代から連綿と続いている崇高な儀式などではなく、1936年のナチス政権下におけるベルリンオリンピックで初めて実施された近代の発明品のひとつである(ナチスは聖火リレーの実施調査をもとに、そのルートを逆にたどって、ポーランドに侵攻した)。だから、旧御射山の神事は「古代オリンピック」と比べられるものではない。というより、そもそも真偽不明の古代オリンピックは西欧文明の普遍性を構築するため現在から過去に投影された神話的起源(つまり自己正当化の捏造物)であるのは論を俟たず、古代オリンピックであるかどうかという視点そのものが倒錯している。
また、オリンピック憲章にもあるように、オリンピズムの目的は、スポーツによる人類平和の推進である。[v] スポーツの権利という普遍的人権の名のもとに、人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的意見、国、出自、財産、身分等を理由にしたあらゆる差別を拝した完全な平等が目指される。そこで聖火リレーというパフォーマンスは、日常の社会的・政治的諸関係の抗争状態から切り離された「平和」のはじまりを告げるものであり、一時的なフェアネス=平等を実現するという役割を担わされている。しかし、言うまでもなく、オリンピックにおける「平和」のヴェールは国威発揚あるいはショービジネスの金儲けという極めて明快な目的を覆い隠すために作られたイメージ=シミュラークルに過ぎない。
諸国家間のみならず、無数の差異の抗争と資本主義の精神を忘却するための、あるいは忘却したフリをするための文化的装置。それが「平和の祭典」である「オリンピック」のごく基本的な政治性であろう。2021年の東京オリンピックでは、日本政府が「今後人類が新型コロナウイルス感染症に打ち勝った証しとして」開催すると宣言した。[vi]ここで「平和の祭典」は新型コロナウイルス感染症の危機は終わらないかもしれないという不安を覆い隠すためのヴェールである。他方、いわゆるリベラル陣営は「人びとの命と暮らしを守る」ために開催中止を要求した。[vii]新型コロナパンデミックで露見したグローバリズムの予見不可能性がもたらす不安を「外国人」の排除=オリンピック中止によって達成する、言い換えればグローバリズムにおける「外」の不可避な混入を忘却するために、オリンピックが掲げる「平和」の理念に反するという否定的な言及において「国民の平和」が呼び出された。
いずれにせよ、聖火リレーが政治的・商業的目的に「平和」という忘却のヴェールを被せるパフォーマンスとして機能するのだとしたら、水のリレーは、そもそも「平和の祭典」を根拠付けている理念的な目的(人類平等)や神話的起源(古代オリンピック)の「なさ」そのものを開示したと言えるのではないか。
水は順々にリレーされていき、最後尾の人間は、カメラの画角からフレームアウトするまで水を運んだ。同時に、各人はGoProというたくみちゃん持参の小さなカメラで、自分が運んでいる手元の水を映し出していた。両方の内蔵メモリで映像を確認してみると、それはどこまでもどこまでも、ある意味ではどこを目指すこともなくただ水が運ばれていくように感じられる。別言すれば、それは無目的性と未然性によって特徴づけられる時間を構成していた。
無目的性は、パフォーマンスによって達成される目的のなさを意味しており、未然性は「事件を未然に防ぐ」と言うように、東京に運ばれうるかもしれないが、いまはまだ運ばれていない可能性の様態を意味している。つまり、現実から平和な時間を聖別するためにおこなわれ、東京の聖火台に向かうことが決定している聖火リレーとは対称的に、「水のリレー」はなにかのために行われているわけではなく、また、どこかに運ばれうるかもしれないという可能態のうちに留まり続ける(気づけば全然関係のない土地に迷い込んでいるかもしれない)。それはなにを成すわけでも、どこに向かうわけでもないものたちのリレーであり、それゆえに国家の公認から除外され、平和のヴェールを剥ぎ取られた身元不明の聖火ランナーを想像させる。
オリンピックから締め出された聖火ランナー。誰もそれを聖火ランナーとは認めないだろう。神話的起源としてのオリンピアに連なる正統性を見るものなどいないだろう。そもそも身分の同一性が保証されない身元不明の聖火ランナーは、危険な浮浪者ともテロリストとも、あるいは失業者とも負け組の落伍社ともUber Eatsのライダーとも呆けた徘徊老人とも見分けがつかない。このランナーはただリアルに遍在する。人類平和の使者ではありえない。
政治的経済的な諸権力に剥き出しでさらされた無数の諸身体と折り重なる「水のリレー」のランナー。しかし器に溜めたいずこから湧き出てくるのかわからない水を人知れず社会のいたるところに撒き散らす、のかもしれない。あたかも諸権力に秩序付けられた社会空間の内部では想像しえない――想像が禁じられた――また別の自生的な〈生〉の環境が生い育つ水のたまりを湛えてみせるかのように。
1-2 リミナリティの橋(武谷)

さてさて前に進もう。それから、祠を前にして武谷、たくみちゃん、前田、村田、濵田の5人による即興的なパフォーマンスが30分ほど行われた。その後、武谷は小川に白い脚立(作業台)の橋をかけて「川」の境界を二度超えるというパフォーマンスを行った。焦らず急がずゆっくりと1度目は四足歩行の人間/動物のどちらともつかない動きで、2度目は蛇のような姿態で橋を這い渡る武谷の身振りはユーモラスな可笑しみに満ちている。
こちらとあちらの境界線上で人ではないものへと変容する過渡的領域を、文化人類学者のヴィクター・ターナーはヴァン・へネップの通過儀礼の理論から抽出した「リミナリティ」の概念で定義している。通過儀礼は、分離(separation)・周縁ないし敷居(liminal)・再統合(aggregation)の三段階で特徴づけられる。象徴的行為を通じて諸々の社会的条件から分離された儀礼の主体は、中間に介在するリミナルな時間において身分・地位・属性が不確定な曖昧な状態に投げ出され、儀礼の終わりとともに新たな社会的規範のもとへ再統合される(たとえば成人式などは儀礼の名残である)。[viii] リミナリティ(境界性)は、リチャード・シェクナーが文化人類学・演劇理論・社会学……の学際的な研究領域として理論化したパフォーマンス研究の基礎概念のひとつとして位置づけられ、「パフォーマンス行為は基本的に過渡的」であり「常に何らかの変容の過程にあって、分類したり定義したりすることができない」とされた。[ix]
こうしたリミナルな〈あわい〉の空間を、武谷はシンプルな「渡る」という行為で発現させる。しかも、「焦らず急がず」という叙述の解像度を上げるならば、行きつ戻りつであり、向こう岸の脚立の足を掴んで降りようとする素振りを見せつつ降りないのであり、武谷は見ていて焦れったくなるほど脚立の踊り場の上に留まり続ける。だが、この行きつ戻りつの反復のリズムがリミナリティを生起させ、あちら/こちら、生/死、渡る/留まる、人間/動物、哺乳類/爬虫類といった意味-感覚の境界が不分明になる場所へと、わたしたちを連れ出すのである。
1-3 宝石デコのミシャグチ(前田)

日も暮れかけたので、一行は旧御射山遺跡から踵を返し八島湿原の木道を通って帰路につくのだが、その途中にある6人がけのテーブルが設置された休憩所で前田のパフォーマンスを収録することになった。日が落ちるのを待っていたらしい。何をするのかと思えば、頭まで覆われた黒の全身タイツに着替えた前田が登場。休憩所の一角に立った姿は、あれです、ショーウィンドウのマネキンです! 頭部にはキラキラした宝石デコシールを貼り付けたオフホワイトの被り物を装着。そして、今朝聞こえてきた、あの美しい旋律が前田の声帯を震わせる。「アヴェ・マリア」(エレンの歌第3番)だ。
デコシールをキラキラさせるために、我々は前田の顔に手持ちのスマートフォンから光を投射。八島湿原の広大な緑の風景をバックに、全身タイツで頭をキラキラさせた人間が伸びやかな手振りを交えてアヴェ・マリアを歌う。こんなことってある?
「あ」の母音のみで発せられる声の震えと共鳴するように、頭の宝石デコがひとつ、またひとつと床に落ち、カツンカツンと音を立てる。そのなんとも物悲しい(?)光景は頭に焼き付いて離れない神妙な時間をつくりだしていた。
被り物といえば、もしかしたらそれは中沢新一がミシャグチ信仰の象徴として論じる「胞衣」と関係しているのかもしれない。この連想について考えてみよう。
諏訪地域には縄文時代から、様々な信仰・文化が地層のように積み重なっており、縄文文化と諏訪信仰のつながりを解明しようとする民俗学的・考古学的な研究が盛んに行われてきた。御柱と呼ばれる巨木を人力で曳き廻し、諏訪大社の各宮――諏訪大社は上社本宮・上社前宮・下社春宮・下社秋宮の総称である――に建立する御柱祭や、上社前宮で執り行われる75頭の鹿の生首を神前に供える――現在は剥製で代用されている――御頭祭といった豪快で血なまぐさい神事も現存しており、これもまた縄文時代とのつながりを連想させる所以となっているようだ。戸矢学の解釈によれば、御柱は諏訪の「古き神」に供物として捧げられた人柱の代用品だったとも言われる。
しかしいずれにせよ、この三日間の滞在が「初諏訪」だった私には、諸説ある諏訪信仰の「実相」について判断する能力も知識も経験もないので、あくまでもパフォーマンスから連想され、パフォーマンスの経験を遡行的に構成する隠喩として中沢新一のミシャグチ解釈に触れてみたい。
諏訪地域一円に広がった土俗信仰として、ミシャグチ・ミシャグジなどと呼ばれる神がいる。御神体は男根を連想させる石棒であることが多く、こうした自然信仰のありようが縄文文化の古層を今に伝えているとも言われる。中沢は『精霊の王』のなかで、(日本の、ではない)「古層の神」に連なるミシャグチ≒シャグジは「空間やものごとの境界にかかわる霊威をあらわす」と解読する。[x] だからミシャグチの表現は石棒だけで成立しない。ミシャグチという神は「石と樹木の組み合わせで表現される」。なぜなら、ミシャグチの境界とは、「世界と生命の根源にあるものに触れている境界の皮膜」を意味しており、樹木が生命力を湛えた境界として石棒を包み込む役割を成すことで、ミシャグチの霊威が表現されるからだ。[xi]
樹木に包まれることで生まれるミシャグチの構造を、中沢は上社前宮の神長官守矢家に伝わる古文書でミシャグチが「胎児」として解釈されていることに着目し、胎児を包み込む胞衣(えな)の形象と重ね合わせている。[xii]胞衣の膜が保護する胎内は子を育てる生命力に満ちている。つまりミシャグチとは包まれる空間の形象でイメージされる荒々しい生命力/生成力/威力といった〈力〉の源泉である。
胞衣の膜が胎内と現実空間の接触面となるように、ミシャグチは霊性を秘めた潜在空間と現実の境界においてもろもろの現象や事物、そして人間を変容させる見えざる力として働く。だから、ミシャグチの〈力〉を震わせ、呼び起こし、活性化する踊りや歌の芸事/パフォーマンスは、人間の世界に富と活力と威力をもたらす。そのような構造を中沢は古層の神の本質にある神話的論理として看取するのである。
ミシャグチ神自身が、「胞衣をかぶって生まれてくる子供」として、けっして「胞衣」を脱がない神なのである。ミシャグチは「胞衣」をとおして、存在の母体とつねに直接に結びあっている童子(小さな子)の神として……たえまなく生成される神なのだ。[xiii]
やや長々と中沢のミシャグチ解釈をパラフレーズしてきたが、こうしたミシャグチ=胞衣の隠喩を介して、キラキラ頭巾を被る前田の姿態を、胞衣を被ったミシャグチの形象として思い起こすことができる。前田のパフォーマンスは、日が落ちて辺りが暗闇に沈む中、キラキラとした宝石/光が浮かび上がるようにと構想されていたようだ。あいにく、日が沈みきることはなく、前田の全身がしっかり見えているなかでのパフォーマンスになったが、それでもキラキラ頭巾と全身タイツに包まれることで不定形の〈力〉を内蔵した身体から発せられる声は、何者でもない非人称的静けさのうちで、ミシャグチの見えざる霊威を触知させるのだ。
しかも「アヴェ・マリア」――聖母への呼びかけとともに。ここでは聖母マリアの非血統的・非人称的な胎――なにしろ処女聖マリアはどんな男とも交わらずに子を成すのだ――とミシャグチの胎が「生命の発生」を介した喩的混淆を結晶させている。いわば、因果的時間に対する生成的時間の系列が呼び起こされるというわけだ。
喩のふくらみはどこまでも連想をつなげていきそうだ。溶岩くぼみに溜まった水に、無数の植物の遺体が分解されずに堆積したのが八島湿原であることを思い出すべきだろう。中沢は、かつての上社では諏訪各地の巨木や石というミシャグチの依代を祀った「湛(たたえ)」を巡行する神事が行われており、それらの場所が水と関係する「タタエ」という語で呼ばれることに注意を向けている。[xiv]「胞衣をかぶって生まれてくる子ども」として絶え間ない声を生成するパフォーマティブな形象は、見えざるくぼみの潜在面から萌えいづる八島湿原と共鳴する。こうした喩のレンズを通せば、キラキラ頭巾から剥がれていく宝石デコたちは、八島湿原という生死が循環する自然のプロセスさながら、声の生成のさなかに生まれては朽ちていく無数の遺体のようにも思い出されるのである。
キラキラ頭巾=胞衣を被った前田は、ミシャグチという見えざる潜在空間の〈力〉とわたしたちをつなぐ器になる。ただし、それはミシャグチが聖母マリアの胎(キリスト!)であるとか、八島湿原に潜むミシャグチ性を前田が表現したとか、前田の全身タイツのパフォーマンスが本質的にミシャグチ的であるとかいうことではない。前田のパフォーマンスの身体=形象が媒介となり、それら連想の網の目がそこに初めて呼び寄せられ、折り畳まれたのだ。いわばすべて妄想であり、捏造である。
しかし、“何者性”を全身タイツの内に潜ませることで不定形の“何者か”として生起する前田の身体=形象は――繰り返すが、これは中沢の指摘するミシャグチの構造そのものである――それを見る者の解釈によって汲み尽くされることがない。またあらゆる解釈に開かれているわけでもない。諏訪のかたちと共鳴する妄想であり捏造を解釈不能なまでにみなぎらせること。言い換えれば、喩の祝祭を立ち上げること。そこにもしかしたら諏訪に/諏訪から複数性の交差路を呼び込むような応答のかたちがありうるのかもしれない。
DAY2 中山道
2-1 模倣する声(村田)

八島湿原から宿に帰ってきた一行は、とりま菅野温泉で垢を落として、居酒屋ゆきの卓を囲んだ。しょうもないが印象深かったのは、いなご・さなぎ、蜂の子の昆虫食を生まれて初めて口にしたことだ。意外にいける。
これで諏訪1日目は実は終わっていない。というかここからがある意味で本番だったのだが、それはそれとして夜が明けて2日目に突入。二日酔いがひどい。この日は、まず村田さんによる「山歩き」のパフォーマンスがあり、私も同行させてもらうことになっていた。前日の飲み会で、「あの山道はきつい」「リサーチで来たときは途中で引き返したからね」などと散々言われ、「大丈夫ですか? ぼく、本当に大丈夫ですか?」というやりとりがあったものだから、万全の体調で望まなければと思っていたのだが、私の頭に鈍痛走る。そうか、昨日の朝にたくみちゃんが辛そうにしてたのはこういうわけか…。
追い打ちをかけるように、ご飯を買うひまもないほどハードスケジュールだと聞かされ、びくびく怯えながらも、私はR3一行の車に乗り込み、和田峠の旧中山道に向かった。ちなみに、私はどこに行くにも車の後部座席になんとなく座っており、乗り込んでしばらく経ったら、見知らぬ山の中に到着している。いきなり別世界に迷い込んだような不思議な感覚だ。
車は旧和田トンネル方面へと向かう国道142号線のかたわらに見えてきた空き地のようなスペースに停車する。周囲には車道と河と山林しかない。これからあの山に登るのか……と思った矢先、「あ! ない!」という牧田さんの声が響いた。一同に緊張走る。どうもメインカメラのバッテリーを宿に忘れてしまったらしい。今日のスケジュールもギチギチだ。取りに帰る余裕はない。どうする。どうしようもない。いや、武谷さんがいる。
というわけで、自身のパフォーマンスの準備のために別行動をしていた武谷さんにバッテリーを取ってきてもらうことに。ホッと胸をなでおろした我々は旧中山道へと足を踏みいれ、和田峠の頂上を目指して歩き始めた。
中山道は、東海道と並んで、江戸と京都を結ぶ旧街道の一つである。和田峠の頂上にある「古峠」の案内板には次のように記されている。
中山道設定以来、江戸時代を通じて諸大名の参勤交代や一般旅人の交通、物資を運搬する牛馬の行き来などで賑わいをみせた峠である。……冬季は寒気も強い上に、降雪量も多く、冬の和田峠越えの厳しさは想像を絶するものがあったであろう。明治九年(一八七六)東餅屋から旧トンネルの上を通って西餅屋へ下る紅葉橋新道が開通したため、この峠は殆ど通る人はなくなり古峠の名を残すのみである。
牧田さんのまとめた「和田峠」に関する資料によると、和田峠は「先史時代には黒曜石の産出地として多くの人々を引きつけ、中近世には遠距離交易の難所として人々の前に立ちはだかった」という。東海道に比して峠道が多く、往来が困難であったと言われる中山道のなかでも、ここの峠超えはいっそう厳しいものであったのだろう。
そしてこれから我々はそんな難所に挑むのである。といっても、しっかりと踏み固められた道は歩きやすく、事前に脅かされていた(?)ほどの困難を感じるものでもなかった。心和む新緑の風景に身を委ねながら一歩一歩足を前に運んでいく。談笑しながら歩きつつ、疲れたら丸太のベンチで一休み。中腹を超えたあたりでは、木筒からちょろちょろと流れ出している清水に口をつけた。山林が減り始める頂上付近になると目の前の視界が開け、山々に囲まれた諏訪の街が一望できるようになる。目を凝らすと、雲の向こうからなにか見知った形の山が顔を出している。あれは……富士山だ! 確信はないが、誰かが富士山だと言っていたので、きっと富士山なのだろう。私の人生初富士である。
そこから、村田のパフォーマンスが始まった。昨日の旧御射山遺跡で初めて目にした村田のそれは、ある種の神がかりを感じさせるものだった。今日はどうなるだろうと期待に胸をふくらませていると、村田は頂上の一角で靴を脱ぎ、白い塗装が施された色紙サイズほどの木の板に四つの小石を配置。そして手持ちのボールペンで小石のまわりに何度も何度も円を描き始めた。まるで枯山水の制作のようである。
それから小石のひとつを手にした村田は、猛烈な勢いで白板をこすりながら「いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい」「いんいんいんいんいんいんいんいんいういいいいいいいいいういいいいいいいいいいいい」と、垂直に突き抜ける〈声〉を響かせたのである。「筆記具」として用いられた小石は、白板に小石の痕跡を刻みつけ、ついには塗装を突き破り、板の木肌を露出させてしまうのだ。
20分以上続けられただろうか、塗装が剥げた白板には独特の木肌の模様が浮かび上がる。RespondingのWEBページに掲載されている村田のプロフィールには、「原初的な身体所作で強いインパクトを与えるドローイングパフォーマンス」[xv] という記載がある。和田峠のパフォーマンスはまさに即興的かつ刹那的なパフォーマンスの遂行が、そのまま剥き出しの木肌の触覚的な模様=パターンを浮かび上がらせるドローイング/パフォーマンスであった。
私はパフォーマンスのあいだ「これは誰の声なのか?」ということに興味を惹かれていた。ここで垂直に突き抜ける詠唱――発語の形式があるので叫びではない――と白板を掻きむしる身振りを切り離して対象化することはできない。単純に言えば、激しい運動がなければ、テンションの高い声は出ないだろう。逆に、テンションの高い声を出す気合がなければ、激しい運動はできないだろう。つまり、村田のパフォーマンスは、声と身振りが渾然一体となった湧き上がる〈力〉そのものを呈示する。声/身振りはそのふたつの現れにほかならない。
したがって、欲動的なエネルギーがそのまま発現する〈声〉のありかは、村田という一個の自我に帰することができない。ではそれは誰なのか? 人間の世界を秩序づける記号の体系に汲み尽くされることのない〈声〉の質量は、知覚しえない何者かの〈声〉を模倣している。
「まったく書かれなかったものを読む」。この読み方が最古の読み方である。つまりそれは、すべての言語以前の読み方であり、内臓から、星座から、舞踊から読みとることにほかならない。[xvi]
かつて、ヴァルター・ベンヤミンは、子どもが風車や汽車の真似をするように、人間には類似を生み出す能力、つまり模倣の能力が備わっていると述べた。歴史の過程で記号的な意味の理解が優勢になり、衰弱あるいは「非感性的な類似」として文字に流れ込んでいった「模倣の能力」は、根源的には内蔵・星座・舞踊などの「書かれなかったもの」を読むことだった。占星術では天体の動きをホロスコープという円形の座標で模倣して未来を読む。同様に、意味作用を持たない村田の〈声〉も、そこにあるなにかを模倣=読解しているのではないか? そうだとしても、村田の〈声〉は何を模倣して、何を読んでいるのだろうか?
和田峠のパフォーマンスを構成する要素のひとつに、ヘッドホンがある。白板の角にはヘッドホンの端子が挿し込まれており、伸びたコードにつながれたヘッドホンが頭上の木の枝に引っ掛けられている。標準的な意味の通念に従えば、この配置は白板=レコードプレイヤーに小石という針を落として、村田の〈声〉を再生するオーディオシステムを構築している。
しかし、実際の印象は逆だ。むしろ村田に――その声/身振りの身体に――〈声〉が再生されている。ここで白板に挿し込まれたイヤホンジャックは、白板を掻く小石の運動を電気信号に変換する通信の隠喩を際立たせ、有線ケーブルは白板を知覚された現実とは異なる位相につなぐものとして感受される。ヘッドホン、ケーブル、端子、白板、小石、村田における身体の姿勢、そして〈声〉が触媒となり、諸々の喩によって構成されたパフォーマンスの場所は、小石の振動がケーブルを通じて枝の先端まで延長され、和田峠そのものと交信するかのような地場を形成するのである。
だから、村田のパフォーマンスはまったく書かれなかったもの、すなわちこの空間に満ちた和田峠の〈声〉と交信=模倣して、それを読んでいる。白板の模様は和田峠の〈声〉の痕跡であり、同時に和田峠が書く文字でもある。小石に掻かれ=書かれ剥き出しになる板の木肌は和田峠を模倣する〈声〉の形象なのだ。言い換えれば、村田のパフォーマンスによって、私たちの可聴域の外に潜んでいる聞こえざる〈声〉が、触知可能な感性的なものへと移行するのである。
しかし、いったい和田峠の〈声〉とはなんだろうか? そこでは何が読まれているのだろうか?
人間は聞いた声を忘れ、そして、後に、それを意味として想起する。このような忘却/想起が、歴史をかたちづくる。歴史化とは、声の忘却であり、名の忘却であり、すべてを意味として思いだすこと、つまり、自分にとっての意味=有用性から思い出すことである。[xvii]
かつて、田崎英明は、宛先を持つ人間の言葉に対して、宛先を持たない動物の声を対置し、瞬間瞬間に滅び行くものたちのあげる〈声〉の模倣が名であると述べた。いま目の前で死にゆくものに対して、私たちは何も出来ない。ただその〈声〉=名を繰り返すことしかできない。子どもが犬を「ワンワン」と呼ぶように、と田崎は説明する。
しかし人間は死にゆくものたちがあげる犠牲の〈声〉を民衆・民族の声として国家の歴史のうちに囲い込む。宛先を持たない〈声〉は共同体の歴史を創出するための有用な意味に変わり、わたしたちはそのかぎりで死者を記憶にとどめ、意味あるものとして想起する。反対に、宛先を持たない無意味な〈声〉は、その名を誰も知らない犠牲者となり、共同体の秘密として――ナチス・ドイツ政権下の失踪したユダヤ人の名のように――秘匿される。
田崎の立論にはやや強引(というか詩的)なところがあるが、言わんとすることは了解可能だ。現在の日本という場所の文脈では、たとえば名古屋入国在留管理局で剥き出しの生として「遺棄致死」されたウィシュマ・サンダマリの宛先を持たない死にゆく声が、公然の秘密として秘匿されていたことを思い起こすべきだろう。〈声〉の秘匿は名を隠すことと同義である。その名を誰も知らない犠牲者は「日本」の境界を画するための他者、「内なる外」として包摂され、その〈声〉はいまだに我々の内部に秘匿され続けている。
確かに、森や鹿や小石といった個物が滅びるときにあげる〈声〉は、「もり」や「しか」や「こいし」ではないが、「森」や「鹿」や……が消えゆくときの〈声〉の残響がそこに残されていると私たちは感じることができる。それは意味として記述できない――無声の声と言いたくなる――“なにか”である。「森」や「鹿」や……という名は、そこに残された〈声〉=“なにか”の似ても似つかない模倣なのだ。
無意味な〈声〉の模倣は、歴史が創出する共同体の現在からは「意味」として思い出せない、秘匿された名=“なにか”の想起を含意する。だとすれば、和田峠の〈声〉に模倣=読解されるものとは、忘却されゆく歴史の声を刻印した、古峠という「名」の記憶にほかならない。
なぜこの場所にはわざわざ「古峠」の名がつけられたのか。考えてみれば、それは奇妙なことではないか。開通された新道との差異をつけるために「古峠」と名づけられたのだと言うことはもちろんできる。しかし、「古峠」の名には独特の質量がある。正確に言えば、村田の〈声〉の質量が「古峠」の名の重みを触発する。「古」を現在の歴史的起源としてではなく、ただ滅びてゆくものたちの忘却された〈声〉を想起させる。
「古峠」とは、「古い峠」に共通する性質を意味する一般名詞ではない。まったく書かれずに忘却された歴史の名である。村田の「いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい……」は、和田峠に満ちた〈声〉の模倣であり、「古峠」に秘匿された名の想起である。村田の〈声〉においては、ただ秘匿され、忘却された「古峠」の“なにか”が模倣され、読まれているのである。
村田の〈声〉は“なにか”を模倣している。これはほぼ何も言っていない貧しい結論だ。しかし、日本あるいは諏訪という共同体の歴史、権威的な威力の中心としてのミシャグチからは思い出せない“なにか”が忘却された古の残滓としていつもすでに秘匿されていることを、少なくともこの貧しさがかろうじて思い起こさせてくれるのではないか。そう私には思われるのである。[xviii]
2-2 「いる」――してもしなくても(濵田)

書けば書くほど長くなっていくという“なにか”の悪い力が働いているので、ややスピードアップして、DAY2の濵田と武谷のパフォーマンスを見てみよう。
無事、村田のパフォーマンスが終わり、山を下りた一行は、車を止めてあるスペースで車座になって昼食を食べ、それから和田峠西餅屋跡地に向かった。ここではもろもろの準備があったのだろうか、かなり長い待機時間を過ごした。次は濵田のパフォーマンスだ。
濵田のそれを端的に言い表すならば、「黒曜石を川に返す」である。車中で聞いた話だが、濵田はリサーチのときに黒曜石を拾った。けれど、その昔、祖母から川で拾ってきたものはちゃんともとの場所に返さないといけないと言われていた。悪いものを連れてきてしまうからだ。そこで今回、黒曜石を入れた箱を小型トラックのラジコンカーに載せて、川まで運んでいくことにしたらしい。
先述したが、和田峠は黒曜石の産地である。縄文時代には、黒曜石の交易が盛んに行われていたという。ただ、この「黒曜石」の観点から、なにかしらが読めるようになるとか、想像力が換気されるとかいうことは、少なくとも私には起こらず――トラックに載せられた黒曜石からは、石灰石の採掘で見る影もなくなった秩父の武甲山をなんとなしに連想するが――その代わりに、濵田のある種の不思議な「やる気のなさのようなもの」が、ずっと私の心を捉えて離さなかった。
パフォーマンスのルートは、ざっくり三分割できる。ひとつは、西餅屋跡地の空き地から国道142号線を横断して中山道の入口まで。次に、緩やかにカーブしながら川へ続いている中山道の下り坂。そして最後に、黒曜石を返す川である。
まず、濵田は荷台に黒曜石を積んだラジコンを操作して、国道142号線を渡らせる。そこから先は山道でラジコンを走らせることはできない。そこでラジコンにオレンジの紐を結わえ付け、トートバッグのように肩にかける。そのまま何かよくわからない白い板を上空に掲げたり、柵の手すりにぶつけたり、印籠のように前に掲げたりしながら、坂道を下っていく。川に到着した濵田は、肩にかけていたらラジコンを地面におろし、先日の「水のリレー」の際に用いた「木彫りの亀の甲羅」をポケットから取り出したかと思うと、それをスコップのように使って地面をえぐり、デジタルメモパッドを差し込んだ。このあたりやや曖昧なのだが、濵田は亀の甲羅で川の水をすくったりした後、デジタルメモパッドに箱に入っていた黒曜石を何度もぶつける。デジタルメモパッドは書いて消せるメモ帳だが、そこに黒曜石が衝突した痕跡が点々とつけられていく。
パフォーマンスの意味生産の場面ではなく、そこで遂行される身体所作のありように的を絞ろう。ラジコンの前面になぜか結わえ付けられていた雑草、ラジコンをトートバッグとして肩にかけるとき、なぜか一度、赤子を背負うように背中に乗せる所作(その後、その姿勢の制約がかけられるわけではない)、いつのまにか持っていた白い板のようなもの、手すりにカツカツとこすりつける無駄な動き、黒曜石をダーツのようにデジタルメモパッドにぶつける謎の所作……正直、そのひとつひとつがよくわからないのだ。そもそも車中で語られたパフォーマンスの動機がよくわからない。あまりに私的な動機に思えるからだ。
いや、そういうこともあるだろう。一見してよくわからないものはいくらでもある。ここで伝えたいのは、その所作のいちいちが、やってもやらなくてもよいが、とりあえずやってみせていますといった風情であることだ。パフォーマンスを構成する諸要素の布置や構造、あるいは身体を媒介したパフォーマティブな意味生産や、なんらかの「身体性」が構築あるいは脱構築されるプロセスといったような、明示的に語りうるものがなにもないような印象を受ける。濵田は、ただそこにいる。いわば、どうでもいいものとしてそこにいる。暴走したり、脱力したり、震えていたり、虚構の身体であったり、生身の身体であったりするわけでもない。ただ、いるのだ。
これをどう考えたらいいだろうか? あるいは私はなにか思い違いをしているのだろうか?またあらためて考えたい問題であるが、ここでは暫定的に、思考の手がかりとなる足場として、バートルビーの形象から、濵田の「いる」という状態の記述を試みたい。
彼を呼んだとき、私はちょうどそのような姿勢で腰掛けていた。そして、彼にやってもらいたいことを早口で述べた――つまり私と一緒にちょっとした書類を点検してほしい、と言ったのである。ところがバートルビーは、自分の私的領域から動くこともなく、特異なまでにおとなしくも堅固な声で「しないほうがいいのですが」と応えた。そのときの私の驚き、いや狼狽を想像していただきたい。[xix]
アメリカの小説家・ハーマン・メルヴィルが19世紀の半ばに創造したバートルビーの形象は、哲学・政治学・倫理学などの諸文脈で取り上げられ、論じられてきた。ニューヨークのウォール街に事務所を構える法律家の書生として雇われたバートルビーは、あるときから「しないほうがいいのですが」と応じて法律家に命じられた業務をせずにいるようになる。
これは単純な拒否ではなく、願望の表明でもない。書類の点検を「やりません」(拒否)と言っているのでも、「やります」(同意)と言っているのでもない。だからこそ「しないほうがいいのですが」の決まり文句は、法律家が暗に期待している、書類の点検をやるべきだという当然共有されているはずの前提を疑わしいものにしてしまう。「驚くべきことだが、いわば正義のすべて、理のすべてが向こう側にあるのではないかとぼんやり思われてくる」。[xx]それは法律家自身に法律家の要求の意味を投げ返すのだ(したがって、法律家はなぜか筆写をやめてしまった上に事務所から立ち退くこともしないバートルビーに対して、自らが事務所を退去するという本末転倒な仕方で動かされ続けることになる)。
「では、なにをするべきなのか」あるいは「したいのか」という問いに対するバートルビーの返答は、
「しないほうがいいのですが。」
「したくないのか?」
「しないほうがいいのです。」[xxi]
法律家はなすすべもない。「する―しない」の選択において暗に前提されていた「〜するべき」という規範的な法の存在――「[私は]慣例と常識にしたがって頼んでいることなのに?」[xxii] ――が暴露されるとともに、最終的には「食事をしないほうがいいのです」と述べて餓死したバートルビーの受動性は、「肯定―否定」の二元論を宙吊りにし、何事かの決定が全的に放棄される非-決定の圏域を開示する。
濵田はバートルビーに半分似ている。濵田のパフォーマンスにおける身体のありかたは、何事かの決定が放棄された「しないほうがいいのですが」の非-決定の圏域において成されているように思えるのだ。
例えば、黒曜石をデジタルメモパッドにぶつける濵田の身振りには気負いがない。行為の枠組み/フレームはあっても、実現されるべき意味/効果が予定されていない。かといって、その場/身体に生じる無意識の流れのなかで自由に新しいことを発現させる即興的な振る舞いでもない。計画的な行為でも即興的な行為でもなく、能動的な意志の働きでも受動的な無意識の発露でもない、つまりここでは、無数の可能性のうちからひとつの現実を行使―決定する能力が放棄され、なにもしないでいられるという能力が行使されている。
こうした「しないでいられる」能力を、ジョルジュ・アガンベンはアリストテレスの潜勢力(dynamis)の議論に依拠するかたちで、非の潜勢力(adynamis)として主題化し、バートルビーの形象を論じている。本稿で必要な議論の骨格を取り出すため、政治神学的な含意を抜いて、その図式だけを描き出してみよう。
アガンベンによれば、アリストテレスはなにかを成すことができる――現実化できる――という意味での潜勢力から、なにかを成さないことができるという意味での潜勢力(非の潜勢力)を区別した。「キタラの演奏家がキタラの演奏家であるのは、キタラを演奏しないこともできるからである」[xxiii]と解説されるように、非の潜勢力は、なにかができる能力を現実化しないままにしておける能力を指している。
現実化しないままにしておける非の潜勢力を持つとは、他でもありえたかもしれない、現実化していない可能性が現実の行為(現勢力)に含まれているということだ。非の潜勢力は他でもありえたかもしれない可能性を開示する。ゆえに、アガンベンは、「存在と無の両方を超出する非の潜勢力という可能性のうちに最後まで留まるということ」[xxiv]がバートルビーの試練だという。そして、「しないほうがいいのですが」という成さないことを成すことは、意志の力によって排斥された、他でもありえたかもしれない「可能性の全的な回復」であり、「存在しなかったものの想起である」と結論する。[xxv]
要するに、他でもありえるかもしれないという(非の)潜勢力が、濵田の「いる」という印象を作り出しているのではないかということだ。別様にありうることの可能性に滞留しているからこそ、どのように――何者かとして――「いる」ではない、ただ「いる」ものとしての身体が知覚可能になっているのではないか。
しかし、このように解釈されたバートルビーと濵田を同一視することはできない。そもそも「しないほうがいいのですが」の人を狼狽させる感覚を、濵田のパフォーマンスから感じ取ることはおそらくない。もっとあっけらかんとしている。半分似ているとはそういうことだ。詳細な検討は後日に譲るほかないが、暫定的に次のように言ってみることはできる。
バートルビーが「しないほうがいいのですが」と命令/要求に対する非-決定の態度――しないことができる非の潜勢力――で応じることから、現勢力(権力)によって否定された他でもありえたかもしれない可能性の全的な回復へと向かったのだとすれば、濵田は「してもしなくてもいい」という内発的な非-決定の態度で応じることから、他でもありえたかもしれない可能性を可能性のままに身体/場へと畳み込んでいる。そこには「しないほうがいい」と表明しうるような「抵抗」の残滓はなく、だからバートルビーの形象のような諸解釈が誘引されることはなく、これでなくてもよかったかもしれないという――あっけらかんとした――偶有的な無名性の感覚が、ただそうである事実としてパフォーマンスの場に刻印される。
ジル・ドゥルーズはバートルビーの形象にあてて「身元保証なき、所有物なき、属性なき、身分なき、特性なき男である」[xxvi] と述べている。それは身元保証や所有物の権利を前提として、それらが奪われたものとしてのバートルビーに「抵抗」を読み取る所作である。
しかしもしかしたら、アガンベンがバートルビーの裏側(あるいは表側)として描いた、人間を剥き出しの生――法権利の外に締め出された生きているだけの生命――に還元するグローバルな生権力の環境と、80億の生命はすべて尊い=個々人は無価値の不安を解消するために動員される強迫的な多様性のビジョン――あくまでもビジョン――において、つまり一方ではいつ死んでもかまわないと脅され、もう一方ではあなただけのアイデンティティを見つけなさいと脅される環境において、いまや奪われているのは、身元保証なき、所有物なき、属性なき……者であることを前提にした、まさにそうした無名性に留まること、これでなくてもよかったがたまたまこれだった〈生〉の固有の秘密を生きることなのかもしれない。
これこれの所属と属性を有した名であるところの偶有的な顕名性(これでなくてもよかったがたまたま渋革まろんだった)ではなく、これこれの所属と属性を有しているわけではない魂であるところの偶有的な無名性(これでなくてもよかったがたまたま〈これ〉だった)がありうると認めること。生命に還元されず、多様性に回収されない秘匿された〈生〉が。
この意味で、濵田の「してもしなくてもいい」投げ出しは、他でもありえたかもしれない非の潜勢力を「しないほうがいい」と否定的なかたちでも現勢化せず、〈生〉の意味=潜勢力を完全に〈秘匿〉する身振りであり、そうすることであらゆる名づけをやり過ごしつつ、事実そこにいる〈これ〉、無名の生命ではない他者を告知する無名性の創出なのだと私には思われる。濵田のパフォーマンスが呈示する無名性に「好ましさ」を感じるのは、おそらくそうした理由があるのだ。
2-3 祭は誰のもの? (武谷)

メインカメラが川に突っ込むという受難はあったが、濵田のパフォーマンスのあとは、武谷のパフォーマンスが行われた。どうもなにかもろもろ準備をしていたらしく、諏訪でのR3体験のなかでは唯一、パフォーマンスの環境となる舞台装置が組まれた、演劇的なスペクタクルであった。
鹿の頭部の剥製と、白く塗装された大ぶりの木の枝を両手に持った武谷は、車がめまぐるしく往来する国道142号線の向こう側に立ち、こちら側に渡ってくるタイミングを伺う。だが、この国道には歩道がない。武谷の真横を乗用車やトラックがビュンビュンと通り過ぎる。非常に危ない。というか、トラックが猛スピードでやってきたとき、「あ、これ轢かれるわ」と私は思った。しかし、とりあえずことなきを得てこちら側に渡ってきた武谷(のちに聞いた話では、車の前に飛び出る予定もあったという)。そのまま私たちのいた空き地の草原を横断し、森と草原を分かつ境界線を作り出している木の柵のところに脚立を立て、最上段まで上って木の枝を左右に振る。そして、どこからか木の枝をいくつも取り出し、柵の向こう側に安置していった。
これら一連の行為の後、武谷は掘り返された土で形作られた円形の土俵(以下、サークルと記述する)に歩み寄る。サークルの周りに立てられた木の枝は結界の役割を果たし、そこが儀式的な場であることを際立たせている。サークルの中央は小さな円墳のように盛り上がり、その上に三方(神の供物としての神饌物を供える台)のようなものが配置されており、器と瓶子(御神酒を入れる器)が乗っている。そして、三方の後ろには、神の依代になると言われる鏡がある。サークルに足を踏み入れた武谷は、鏡の後ろに鹿の剥製を置き、何度かサークルを巡ると、手に持っていた皿のようなものを三方の前に置いた。
簡易的な祭壇が作られ、決められた手順を遂行する儀礼的なパフォーマンスは、武谷を神主とした奉納の神事を思わせる。鹿の剥製が主役となるように構成されたパフォーマンスであることから、鹿を神饌・贄として捧げる御頭祭を参照していることが伺える。しかし、鹿はあくまでも供物である。鏡の後ろに祀られ、武谷が立つサークルの正面を向いているというのは、本来であればおかしなことだが、この異化効果が武谷のパフォーマンスの混淆的な性質を端的に表している。すなわち、これは誰の祭りなのか? という問いがここに示されている。
森田玲は『日本の祭と神賑』という著書の中で、「神賑行事から『神』の文字を取ると、単なる『行事=イベント』になってしまう」[xxvii]と指摘して、「カミとヒトとの乖離」にまつわる危機感を表明している。
ヒトがカミを奉る行為が祭であるならば、究極的には、祭はヒトのものといえるであろうか。たとえそうであったとしても、現代に生きる我々だけのものではないはずである。祭は過去から未来まで、地域の人々の中で世代を超えて共有されるべき「祈りのかたち」「喜びのかたち」であろう。[xxviii]
私は祭りの喪失が日本人の魂の衰退であるといった森田の主張にはまったく賛同しないが――その日本人とは誰のことなのか、共有されるべき伝統とは現在進行系の支配と抑圧の歴史ではないか――、「祭はヒトのものといえるであろうか」という問いを、私はまさに武谷のパフォーマンスから受け取ったのだった。
御頭祭との関係は定かではないが、ひとつの補助線として折口信夫を召喚しておこう。折口によれば、「まつり」の本義は神の言葉を唱えることだった。のちに唱え言をして収穫を見せるまでが祭事となり、「仰せの通りに出来ました」と言って、生産品を「奉ること」が「まつり」を意味するようになった。[xxix] さらに神の祝詞は五穀を育む力を持っていると信仰され、それを唱えることで人は神と同格になり、神言の伝達者になるのだという。
この神を迎える立場の代表が「主」だ。しかし、「主/あるじ」は元々、人のことではなく、常世神に捧げる馳走を指していた。これが転じて、常世神を迎える人を指すようになった。[xxx]
鹿を中心にした武谷のパフォーマンスでは、鹿は神への捧げものとしての構造的な位置を持っていない。むしろ鹿は祭壇に祀られており、ここで祀られた鹿は「諏訪」のスペクタクルの中心として消費される広告的なイメージ、諸メディア(テレビやネット)に媒介された自然のシミュラークル=剥製でしかないことが明かされている。であるならば、ここでは何が捧げられているのだろうか? あるいは、武谷という「主」が、神への馳走に転じて、捧げられているのではないか?
武谷はこのあと、顔を白塗りにして、スコップで土を掘り返し始める。すると、土に埋まっていた大量の白い粉が舞い上がり、武谷は白い粉が混じった土の上を転がり、あまつさえ、鹿の頭部を持ち上げ、取手の部分を服の中に入れ始める。ある意味では、鹿と合体し、鹿と自分の頭を象徴的にすげ替える。
前日の旧御射山遺跡におけるパフォーマンスでも、「橋」をモチーフに、人と動物の境界が不分明になるリミナルな空間を開示していた武谷であるが、ここではより直接的に鹿と人間のキメラ的形象を出現させ、どちらが「贄」であるのか定かではない混淆的な儀礼の形態を立ち上げるのだ。
もちろん、そのような混淆が可能であることそれ自体が、御頭祭の歴史的文脈から贄としての鹿のイメージ=剥製を分離することなしにはありえない。この情報化社会において、祭は人のものでも神のものでもなく、メディアのものなのだから。だが、武谷はそれに正面から異を唱えるのではなく、むしろまがいものの儀礼と、それを遂行する自己自身を引き受けることで、偽物と本物の境界線上に自らを投げ入れようとしているのではないか(車道に飛び出るつもりがあったという武谷の発言は、この見地から解釈されるべきだと私には思われる)。それは本物(神のもの)とも偽物(メディアのもの)とも言えない、メディア化した人間と神のいまだ知られざる関係の再発明である。
祭事を観光資源とした文化の商品化=イベント化はおよそ避けがたい。しかし、武谷はローカルな儀礼の参照=引用的再提示から、共同体の文化的記憶の内部にパフォーマティブな撹乱=「外」を持ち込む。そして、その儀礼を形成している諸要素の組み換えと再編成で混淆的な儀礼のパフォーマンスを編み上げる。こうした芸術的・文化的実践は、過去から未来まで共有されるべき伝統とは異なる「祈りのかたち」「喜びのかたち」を生み出すことにつながるのかもしれない。
2日目のスケジュールは消化された。木のそばで瀬籐さんが眠っていた。夜は昨日とまた別の銭湯に行った。毎月26日は「ふろの日」だった。一軒目は閉まっていた。二軒目は空いていた。宿への帰りは村田さんと並んで歩いた。
DAY3 諏訪大社上社前宮
3-1 子どもの遺棄と歓待(前田、竹元)

二日酔いにはならなかった3日目である。昨晩はなにかの量を控えめにしていたのである。
3日目は、いよいよ(?)諏訪大社上社前宮へと出向き、前田とたくみちゃんのパフォーマンスが行われた。ただ、わたしはこの時点で、諏訪大社が四宮の総称であることを知らず、そもそも諏訪大社が御柱祭や御頭祭と関係していることも知らず、今日もまた「ここどこなんだろう」というぼんやりとした意識で駐車場に降り立った。
鳥居をくぐると、緩やかな階段が続く。前田さんはダンサーの竹元さんと一緒に、諏訪の子供たちとの共働プロジェクトを進めていたらしく、階段の上で参加者の面々――4人の子供たちと親御さん――と合流。上社前宮の拝殿前を通り過ぎた一行は、そのままコンクリートで整備された道を登り、拝殿のうしろをぐるりと迂回するかたちで、木々が鬱蒼と茂る山道へと入る。するとそこには迫力ある――神妙なると私はいいたくなってしまうが――大木が鎮座している。案内板には「峰たたえのイヌザクラ」とあり、この道を現人神として祀られたが通っていたと紹介されている。二つに分かれた幹の前に御柱に囲まれた小さな祠もあり、ここがミシャグチを祀った「たたえ」であることがわかる。
こうして一行は、もうしばらく行った先にある休憩所にパフォーマンスの拠点を構え、前田の考案した「あいうえおの歌」を用いた子供たちとのパフォーマンスが開始された。
ちょっとした広場のようになっている場所で、カメラのセッティング。ただ、子どもたちはコントロール不能である。坂を下ったところにある前宮公園に設置されている遊具を発見した子どもたちは猛スピードで坂を駆け下りていく。とてもうれしそうだ。そして帰ってこない。役割分担はわからないが、竹元さんが子どもたちのまとめ役を担っている様子であるけれど、パフォーマンスの方へと誘導することに四苦八苦されていた。
そのあいだも、リハーサルで前田さんは「あいうえおの歌」を何度か歌っている。非常にシンプルかつキャッチ―なメロディで、歌詞そのものは「あいうえおかきくけこさしすせそ……」と「ん」まで50音を口にしていくだけであるので文字に起こすことは到底できないのだが、私はこの原稿を書いている今でもそれを口ずさめる。耳に残る音だ。
ようやく、子どもたちが帰ってきて、パフォーマンススタート。前田は持参のポータブルスピーカーにマイクをつなげて「あいうえおかきくけこ♪」と歌い、竹元と子どもたちが事前のWSで制作したカラフルでファンキーな色合いのシャツを着て踊る。さまざまなものに擬態する賑やかな動きであるが、やはり子どもは制御不能である。「あいうえお」に合わせて動きを揃えるなんてことはない。しかし、「あいうえおかきくけこ♪」は場の通奏低音となって持続しているため、竹元のファシリテートで子どもたちの踊りはときおり「あいうえお」のリズムと調和することもある。私はこのような奔放で制御不能なエネルギーを単に好ましく感じながら見ていたのだった。
個人的な経験の話になるが、以前に私はイギリスの劇作家エドワード・ボンドが1980年代の冷戦期に執筆した『戦争戯曲集』3部作に関わったことがある。「核戦争」をモチーフにした連作戯曲の第一部「赤と黒と無知」は、子宮の中で被爆死した「怪物」のモノローグで始まる。
怪物 私たちは、まだ子どもが生まれないうちから子どもたちのことを語り/まだ子どもたちを手に抱くこともできないうちから子どもたちを抱え運び……機械工、家政婦、石工、操縦士、設計技師、管理者、運転士、庭師の手がひとつになり子どもたちを受け取る……これほど準備を重ねて就任する大統領はいない/これほど歓迎を受ける勝利者はいない/驚くほどのことではない、かつて子どもたちが世界は神々によって見守られていると考えていたとしても/しかし今や私たちは子どもたちを殺す[xxxi]
核戦争の終末論に――そしてもはや原爆の大量虐殺に――以前ほどのリアリティは存在していないだろうが、日本でも18歳の子どもが自宅トイレでひとりで出産した子どもの扱いに困って放置し、死体遺棄容疑で逮捕された事件の報道があったのは記憶に新しい。それだけではなく、遊びで熱湯をかけられる虐待の末に「遺棄致死」された子ども、凄絶ないじめの末に失踪し、真冬の公園で自らを自らの手で「遺棄」して凍死した子ども、可視的・不可視的に「今や」「今も」世界には「子どもたちを殺す」環境が偏在している。子どもたちは、明確な殺意や暴力によって殺されるのではない。子どもを見守り、歓迎するはずの社会から見棄てられて殺される。そして私たちはそれを殺害ではなく、あたかも自然死であるかのように容認する。
「あいうえおの歌」のパフォーマンスから、なにを大仰な話を、と思われるかもしれない。私がここで言いたいのは、の構想――ボンドは非人間的な世界でいかにして人間でありうるのかと問いかける――は子どもたちの歓待から始まることを、ボンドの戯曲は教えてくれるということだ。意味へと組み上がる前の自由な素材/マテリアルとしての「あいうえお」は、気まぐれで奔放な子どもたちのエネルギーを包み込む樹木になる。このような無条件に包み込む態度を具体的な上演の技術や環境として体現することは、私たちが依拠する/すべき公共性の基盤をあらためて意識させ、社会のありかたに対する感性的な省察の場を設けることになる。未来は未来の可能性――子ども――とともにつねに再演されねばならず、それによって私たちは胎児を怪物に変貌させないための技術と倫理を受け渡されるのだ。
さらに、前田と竹元は、「峰たたえのイヌザクラ」前の道を舞台にした、もうひとつの共働パフォーマンスを準備していた。例のキラキラ宝石頭巾を被った前田は、ちょうどタタエを見下ろせる場所で、「アヴェ・マリア」を歌う。そして、タタエのところにゆっくりとした足取りで現れた竹元が、モダンダンス的な、周囲の環境との感情的な調和を奏でる即興的なムーブメントで、自然の流れのうちに自らの身体を解放していく。そこに前田の声が、森にこだまする鳥の鳴き声に混じって微かに聞こえてくる。もはや人間が歌っているのか、自然が歌っているのか、どちらなのかあいまいになる境界の圏域(支配力の及ぶ範囲)を露呈させるのだ。
DAY1の前田のパフォーマンスを、私はミシャグチとの関連で注解したが、タタエで行われたこのパフォーマンスは、より直接的に前宮に隣接するタタエの自然を包みこむとともに、その自然によって包み込まれる胞衣的=境界的な圏域を生じさせていた。人の領域を整序しようとする歌と踊りのパフォーマンスは、自然の混沌とした豊穣さを包み込み、また同時に自然に包み返される。「包み―包まれる」緊張関係が境界の圏域を露わにするのである。
単純かつ感覚的に言い直すならば、無意味=混沌とした「自然」が「神妙な森のざわめき」と名指しうるものとして人間である私において立ち現れましたということだが、そうした感覚の発生源は、「包みこむことで包まれる」「包まれることで包む」という人間的なものと自然的なものが相互に秘匿し合う入れ子構造に求められるのであり、互いの潜勢力(ポテンシャル)を受容する「包み―包まれる」空間の開けによって可能になるのだ。
3-2 過剰飽和の現前(たくみちゃん)

さて、この旅程最後のパフォーマンス、トリを飾るのはたくみちゃんだ。私はここで二度驚く。一度目はリアルで。そして二度目はバーチャルで。
休憩所に戻ってきた一行だが、もう時間がない。前日には「明日は余裕そうですね」という雰囲気を醸し出していたが、意外にスケジュールが押している。さらに濵田が「ハルピンラーメン」なるものを見つけた、ぜひ行きたいと燃え上がらせる情熱がメンバー間に伝染していき、もともとの予定にはなかったハルピンラーメン店の来訪が至上命題になっていたのだ。たくみちゃんは、また別の場所に移動することを考えていたようだが、それではハルピンラーメンを食べられない。しかも天気は崩れ始めていて、雨が振りそうな気配。思案の結果――やや複雑なのだが――たくみちゃんは、別の場所に移動しようとしていたが、実はその別の場所がここであったことに気づき、そのままこの場所でパフォーマンスをすることになったのだった。
たくみちゃんは、COVID-19の蔓延から開催中止となったR3の代わりにオンラインで実施され、10名以上のアーティストが参加した「Performance at Distance」に、「100分のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する」という作品を発表していた。今回は、同コンセプトの作品を、上社前宮の土地で展開しようというのである。
タイトル通り、パフォーマンスはきっかり100分行われる。1時間40分であるから、意外に長丁場だ。そのあいだ、たくみちゃんは休憩所から四本の御柱が建てられた拝殿までの広域を用いて、10分に編集するための100分の映像を手持ちのGoProで撮影しながら、いわば自撮りインプロを展開していった。
初発から「俺はミシャグチだ!」と叫んだたくみちゃんは、近くの大木にセミのように取り付いたり、「アメーバ」などと口走り、ぐねぐねとした軟体動物のような表現主義的な動きを見せたりしながら、タタエの方面へと移動し、拝殿の横を流れる川をまたいで、やはりグネグネと両腕を振り乱すような不可思議な動きを成しつつ、一歩一歩前に進み、御柱の前に立つと、雑草の茎を折って、御柱を囲む柵の上にひとつひとつ置いていく。等間隔に並ぶ長短不揃いの茎は、自然の暗号を伝えるモールス信号信号のようだ。
拝殿を参拝したたくみちゃんは、いきなり全力ダッシュ。一行はこれまでの道程をたどり消えていくたくみちゃんの後ろ姿を見送った。そんななか、私はできうるかぎり駆け出し、たくみちゃんを追跡する。すると、休憩所まで戻ったたくみちゃんは、そこの机をステージにして、実質ひとりで即興ラップを披露。「ざざざざ」という砂嵐の擬音から、「ざらざらやまあらし……とげとげ……ゲットゲット……ほげほげ……おぎゃおぎゃ……ほっけーほっけー……北極のアンテナショップ……北極のアンテナショップのそんなミュージックを作曲」「天気持ったよ、天気持った持った持ったたもたもたもたもたもでうどん」などと言葉の音響的な物質性から遊戯的な意味の生成変化をもたらしていく。
たくみちゃんの即興的な生成変化の〈力〉に、中沢新一が解釈するような身体を境界面としたミシャグチ的な潜在空間の現れを洞察することもできるだろう(DAY1-3を参照のこと)。DAY2-2で述べたアガンベンがアリストテレスの潜勢力に、「成すことができる」と「成さないことができる」という二種の区別を見出し、後者の非の潜勢力が他でもありえたかもしれない可能性を現勢力の働きのうちに保持するという純粋な潜勢力の形式からたくみちゃんの即興を説明することもできるだろう(だから――言うまでもないかもしれないが――ミシャグチの〈力〉の構造を純粋な潜勢力として解釈するロジックは、大枠としては妥当性を持つ)。
しかし、ここでは視点を変え、小田部胤久による「微小表象」の解説を参照して、たくみちゃんの「過剰飽和な現前性」と言えるものについての、暫定的かつ簡易な思考の足場を組み立ててみたい。
小田部によれば、バウムガルテンが「可知的なもの」と「可感的なもの」の階梯を覆して「感性の学」としての「美学」を構想したときに依拠した「渾然とした認識」に関わるのがライプニッツの「微小表象」である。「微小表象」とは意識のうちにありながら意識されることのない表象、反省的意識が働く前の表象を意味している。[xxxii]小田部はライプニッツの微小表象の認識をいくつかの側面に分類しているが、そのなかでも「海のざわめき」と「何かはわからないもの=曰く言い難いもの」に関与する微小表象について確認しておこう。
第一に、閾値以下の表象という意味での微小表象がある。海のざわめきを構成する個々の波のざわめきは聞こえない。しかし、これら小さな波のざわめきが合わさり「渾然とした集合」を成さないかぎり、海のざわめきとして認識されない。このように、微小表象は感官の閾値を下回るために気づかれないが、それらの集合において意識的な知覚を構成する。[xxxiii]
第二に、意識されざる計算という意味での微小表象がある。作品のよしあしは認識できるのに、その理由を示すことができないとき、その作品には「曰く言い難いものがある」と言われる。だがそれは理由がないことと同じではない。音楽の美が数の調和の計算に基づくように、意識されざる計算が「曰く言い難いもの」を構成している。[xxxiv]
ぐねぐねとした軟体動物のような即興的な動き、声の物質性から自己生成される即興ラップといったたくみちゃんのパフォーマンスに特徴的な方法ないし表象は、一見したところ曰く言い難い渾然とした表象に見える。いわば内発的に湧き上がる力を、質量の塊にして吐き出しているように思える。そこには方法も形式も構造もないかのようだ。
しかし、それがパフォーマンスを秩序づける構成的な形式を持たない「塊」に見えるのは、実は「海のざわめき」のごとく、感官の閾値を下回るために意識されない無数のイメージの渾然とした集合であるからではないか? おそらく、それらの表象に孕まれている閾値以下の「小さなざわめき」――無意識下で高速処理されている情報=ノイズと言い換えることもできる――を出力する方法が、「100分のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する」という形式的な手続き/アルゴリズムなのだ。
たくみちゃんのパフォーマンスは、100分のシークエンスで完結するわけではない。この後、自分のパソコンに100分間の映像を取り込んだたくみちゃんは、それを10分間で10分に編集するパフォーマンスを実施する。そして魔法のように(!)、10分きっかりで10分の映像作品を創造する。
完成した映像作品は、画面上で四分割される。左上から時計回りに「100分のパフォーマンスを10倍速で再生した映像」「100分のパフォーマンスを10分に編集するたくみちゃんを映した映像」「100分のパフォーマンスを10分に編集した映像」「100分のパフォーマンスを10分に編集する映像編集ソフトの画面をモニタした映像」が同時再生される。ややこしいように思われるかもしれないが、実際にややこしいのだ。左上と右下は実際に撮影された映像の「10倍速」と「10分編集」、右上と左下は編集作業に関わる「たくみちゃん」と「画面モニタリング」と、対称的なセットで構造化されている。
この映像作品が圧巻なのだ。作品内で流れている音は「10分編集」のものだが、その音と四種の映像、そして映像同士の視覚的印象が相互浸透を起こして、四種のどこにも属さない、いわば〈虚〉に属する第五の時間を生成する。
可能態から現実態への移行は、過去から現在に流れる時間の運動を規定する。しかし、〈虚〉の時間においては、四つの映像=時間にバラバラに解体された「現在」と「過去」が入り乱れ、現在化する現勢力(いま)のうちに複数的な非の潜勢力(いつか)が露出する。つまり、「いま」が「いつ」なのか、「それ」が「どれ」なのか不分明になる混沌とした時間が到来する。時間の蝶番が外れてしまうのだ。そして、四種の映像=時間の衝突と相互浸透がもたらす暴力的で猥雑な時間の生成は、認知限界を超えた「過剰飽和の現前」を示している。
「過剰飽和の現前」は単なる無規則なデタラメではない。例えばセミの抜け殻と大木に張り付くたくみちゃん、アメーバと木々のざわめきと死にかけた蝶々の羽ばたき、生と死、たくみちゃんの手の振れが伝播してロープにぶら下がる「倒木の恐れがあるため迂回路をご利用ください」の注意書きが揺れ、画面が揺れ、水の轟音と同期する編集ソフトの音量メーターが振れ、御柱と人柱の身体と休憩所のテーブルに倒立するたくみちゃんの口から発せられる語音と川とうどんが自然の暗号を連鎖させる……これらの意味的・形態的類縁性が折り重なる「過剰飽和の現前」が、意識されざる計算が構成する「曰く言い難いもの」として現れる。それは四種の映像におけるもろもろの運動・事物の意味的・形態的類縁性を重ね合わせる「たくみちゃん」という演算処理機械による計算=出力の結果なのだ。
この地点から、「軟体動物」や「ラップ」の即興を見返してみるならば、それは「100分のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集する」アルゴリズムで出力された過剰飽和をあらかじめ懐胎する身体であったことが、遡行的に明らかになる。「小さなざわめき」の微小表象が多数孕まれていたからこそ、編集の手続きを通じて過剰飽和を示すことも可能になるからだ。
逆に言えば、たくみちゃんの即興は、時間の蝶番が外れる〈虚〉の時間ではじめてあらわになる微小表象の過剰飽和を〈いま〉に現前させることを企んでいる。これまでの考察に一定の説得力があるならば、そう考えることはそれほど的外れでもないだろう。ただ、その場合、感官の閾値未満という微小表象の定義からして、そんな知覚不能な〈いま〉が到来するとはいったいどういうことなのかをさらに思考する必要はあるだろう(もちろん、100分のパフォーマンスをきっかり10分間で10分に編集するパフォーマンスは、その見事な答えのひとつである)。
終わった。これですべてだ。しかし、まだ、残っている。ハルピンラーメンだ。
果たして一行は、ハルピンラーメンを食することができたのか。下諏訪から各地に帰還する終電の時刻は迫っている。ハッキリ言って、もう間に合いそうにない。たくみちゃんは本当に間に合わないので、ひとり先に駅に向かった。疲れ切った一行は、とりあえず車に乗り込んで……。
ここから先の展開は、ご想像どおり。野暮な蛇足の尻尾は切って、ここらでお開きといたしましょう!
4 〈秘匿〉の身振りとスナックの夜
さて、しかし、最初に予告したとおり、ここから少しばかり「秘密結社みたいだな」と感じられたことの意味を明らかにしておきたい。あらためてRespondingとはどのようなプロジェクトであるのかを振り返ってみよう。WEBページには、次のような記載がある。
本事業は、諏訪盆地とシンガポールを複数文化の交差路として理解し、異邦人の他者性が反転して新たな文化を生成する局面に光を当てる。このように複数文化が交流する「場」に焦点を当てて、新たな芸術表現の可能性を探ることは、情報通信技術の発展とともに拡大しつつある国際的な文化交流の可能性と課題を、具体的な空間に位置づけて検討する契機となるだろう。[xxxv]
Respondingが情報通信技術、つまりは90年代以後、インターネットという通信技術の急速な普及から世界中に張り巡らされたグローバルな電子メディア環境を積極的に活用していることに注目すべきだ。Respondingは、そうした新しい情報環境を基盤にした間文化的パフォーマンス実践なのである。
私はこれまで京都・東京の「小劇場演劇」と呼ばれるジャンルに――しかもそのなかでもいわば周縁に位置する諸実践に――コミットしてきた自覚がある。その限定されたパースペクティブの内部からの見解になるのだが、例えば最近ならば東京芸術祭の枠組みで実施されているアジアのアーティストの相互交流と人材育成を目的としたAPAF(Asian Performing Arts Farm)や、座・高円寺が主催するアジア各地から集った舞台芸術家の公開デモンストレーションを基軸とした “one table two chairs”meetingといった公共の劇場・フェスティバル主導の間文化的な相互交流のための芸術的プラットフォームは確かに存在している。
しかし、そうした公共事業として推進されるわけではない、いわば裸の個人間のネットワークを基盤として、アーティスト主導で運営されるプラットフォームが構築されていることを私は知らず、単純に驚いてしまった。そのコミュニケーションのインフラを提供しているのが、FacebookやTwitter、Instagramといったデジタルメディアのソーシャルネットワークなのだ。
デジタルメディアのソーシャルネットワークは、「コミュニティ」を単位とする複数の社会/共同体が複雑に絡まり合うハイブリッドなコミュニケーション空間を結実させた。インターネット普及期のように、電子的(ネット)/物理的(対面)なコミュニケーションのチャンネルが、互いに切り離された別々の回路としてあるわけではない。それどころか、インターネットのつながりが対面的コミュニケーションの補助的な役割を果たしているわけでもない。電子的/物理的なコミュニケーションが相互に絡まり合いながら、より濃密な関係性を構築する手段として用いられ、その混淆的コミュニケーションを基盤とした協働実践が可能になったのだ。こうした視覚から、Respondingというプロジェクト/団体の越境的な性格を枠付けてみることができるだろう。
しかし、新型コロナウイルスパンデミックで、2020年のプロジェクトは延期となり、2021年は「日本国内在住の参加アーティスト及びリサーチャーのみでの活動」になった。帰属や同一性を超えた、間文化的なパフォーマンス実践が持つ直接的な交流の可能性は、新型コロナウイルスによってネガティブな不安の契機に反転した。いわば、不確実性と予測不可能性を特徴とするライブパフォーマンスは結果が予測できないリスクとして「防衛」されるべき対象のひとつになったのだ。結果的に、国境を超えた直接的な交流の道は閉ざされ、2021年は諏訪のみに軸足を置いた、原則非公開の少人数でのフェスティバルになった。
それでは、地域との交流すらも難しくなった今回のR3において「パフォーマンスアートを通じた社会的課題への応答」は成されなかったのだろうか? 仲間内に閉じたフェスになってしまったのだろうか?
ある面では、そう言える。身体を介在させる接触は禁止されてしまったのだから。しかし、また別の見方をするならば〈秘匿〉の身振りによって成立する〈場〉のポテンシャルが引き出されたとも言えるのではないか。DAY2-2で触れたように、〈秘匿〉の身振りは、その人の〈生〉を完全に隠してしまう。なにをしているのか、考えているのか、よくわからないものにしてしまう。しかしそれは、なにかしらが共有されているというある種の幻想を断ち切って、現にそこにいる無名性の他者を創出することでもある。現にそこに「いる」とは、孤立した現実を指していることもあるが、同時に、他でもありえたかもしれない可能性が畳み込まれた存在としての他者を認めることでもある。
新型コロナウイルスパンデミックが露呈したように、ただ生命しか〈生〉の価値を慮る基準がなくなってしまえば、私たちは永遠に他者と顔を合わせる喜びや悲しみと無縁のまま、宴会を開くことも、語り合うことも、予測不可能なパフォーマンスに曝される危険と変容の可能性に身を置くことも、すべては無用の産物になってしまう。〈他者〉に曝される危険を犯すことは、単に計算可能/不可能なリスクを引き受けることではない。さまざまなかたちの他でもありえたかもしれない可能性に開かれること、越境と変容が生成する特別な時間を経験することでもある。そうした〈生〉のありかたが、生命だけを価値基準とした社会では忘れられてしまう。栄養補給と労働と金儲けの快楽の無限のサイクルを回すだけの社会では。
現にそこに「いる」他者との信頼を紡ぎ、秘匿された親密さのうちで関係すること。それは内向きに閉じたコミュニティの形成ではない。むしろ、現にそこに「いる」他者との関係は、「人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的意見、国、出自、財産、身分等」からではない場所で対話と協働を紡ぐことであり、同時に、仲間意識や帰属意識を持たない人々のあいだの緊張関係を、開かれた配慮や遊びを媒介にして多種多様な親密圏のネットワークの形成へとつなげていく地道な歩み寄りである。Respondingはこうした親密圏のネットワークを拡げていく、まさに地道で貴重な実践なのだ。
パフォーマンスの〈秘匿〉する身振りは、共にするもの、共にする場所における平等ではなく、なにも共有するものがないものたちの反転した平等において、各々が「いる」ことを可能にする。人気のない道、山、森で展開されたR3のパフォーマンスでは、「ミシャグチ」や土地の記憶、そして未来と響き合うさまざまな謎が生成された。つまりは〈秘匿〉の身振りが潜んでいた。だからこそ、私は「いる」ことができたのだし、私の口からは「秘密結社」の四文字が芽吹いたのである。
私は私なりのかたちで、それを言葉にして語り直すことを試みた。しかし、ひとつ語り落としたことがある。それはR3の欄外にひっそりと書き残されるべきことがらであったからだ。パンデミックのさなかでは禁じられた遊び。それゆえに、現に来てしまった異邦人=他者を客人として歓待する場となった、「いる」を寿ぐ小さな祝宴。騒ぎに騒いだスナックの夜である。
スナックの夜。そのスナックはどこの誰とも知らないわたしたちを「まぁ、いいでしょ」と迎え入れた。わたしたちは、広いとは言えないスペースに密着して座り、酒を飲み、煙草を吸い、あまつさえ、中森明菜の「DESIRE」をデュエットで熱唱したのである。あるものは酔いつぶれ、あるものは眠りこけ、またあるものは意味不明なうわ言をつぶやいた。少なくともわたしが滞在していた3日間、わたしたちは夜な夜な必ずそのスナックに訪れては、無為な祝宴に興じたのだった。
[i]https://r3.responding.jp/r3-scape-city/
[ii] したがって、いくらパフォーマンスに触発された身体的経験を重視するといっても、諏訪とシンガポールの往還体験を持たないわたしの記述は、どこまでも片手落ちにならざるをえないことを断っておきたい。
[iii] 詳細はリビルセンタージャパンのホームページを参照のこと。http://rebuildingcenter.jp/aboutus/
[iv] http://kyodoshi.com/article/5915
[v] 「オリンピック憲章」、https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2020.pdf
[vi] https://www.asahi.com/articles/ASP785X16P78UTFK00Y.html
[vii] https://www.change.org/p/人々の命と暮らしを守るために-東京五輪の開催中止を求めます-stoptokyoolympic
[viii] ヴィクター・W・ターナー『儀礼の過程』、冨倉光雄訳、ちくま学芸文庫、2020年、pp.150-153。いわゆる伝統的部族の宗教的な儀礼は強制的な義務として課せられ、不可逆的な変容をもたらすが、そうしたリミナルな儀礼に対して、芸術や余暇といった一時的変容をもたらす任意参加の儀礼の形態はリミノイドと定義される。現代日本の成人式はもとより、ジャンルとしての演劇やパフォーマンス・アートもリミノイドに該当する。
[ix] リチャード・シェクナー『パフォーマンス研究 演劇と文化人類学の出会うところ』、高橋雄一郎訳、人文書院、1998年、p.74。
[x] 中沢新一『精霊の王』、講談社、2003年、p.58。
[xi] 同書、pp.59-60。
[xii] 同書、pp.63-66。
[xiii] 同書、pp.66-67。
[xiv] 同書、p.61。
[xv] https://r3.responding.jp/participants/mineki-murata/
[xvi] ヴァルター・ベンヤミン『ベンヤミン・コレクション2』、浅井健二郎編訳、三宅晶子、久保哲司、内村博信、西村龍一訳、ちくま学芸文庫、1996年、p.81。
[xvii] 田崎英明『無能な者たちの共同体』、精興社、2007、p.39。
[xviii] 本文には組み込めなかった、村田のパフォーマンスの欄外に記されたエピソードをここに残しておきたい。欄外といっても、それによってパフォーマンスの見え方は一変するかもしれない。村田がパフォーマンスで使った小石は、山登りの最中、ずっと靴の中に入れられていたのだ。また、カメラが上向きになるように、靴にスマートフォンを装着して、Facebook LIVEで生配信を行っていた。その記録をのちに見た私はバチバチに感動してしまったのである。これは「小石の経験だ」と。LIVE映像は、まさに小石から見た世界を映し出しているように思われたのだ。カメラ=小石が揺れ、森が揺れる。反復のリズム、踏みしめのリズム、踊る小石の酩酊! 山を登るとは踏みしめの酩酊なのだ。それはまた「山を登る」の表象からは隠されてしまう一歩一歩の不断の反復を思い起こさせる。時間の生成/時間の経験が組織されるあり方が、記憶のうちに表象された「山を登る」とはまったく異なっている。いまやあまりにも単純で当たり前に思える、記録装置が生み出す現実との疎遠な距離が、時間表象の全体性に破れ目を作り、引き延ばされた逐次的な時間――時計の秒針をじっと眺めているような――を産出する。そしてそれは非人称的な小石の経験を私たちにそっとささやき始めるのである。
[xix]ジョルジュ・アガンベン『バートルビー 偶然性について 附ハーマン・メルヴィル「バートルビー」』、高橋和巳訳、月曜社、2005年、p.107。
[xx] 同書、p111。
[xxi] 同書、p116。
[xxii] 同書、p.110。
[xxiii] 同書、p.15。
[xxiv] 同書、p.53。
[xxv] 同書、p.75
[xxvi] ジル・ドゥルーズ『批評と臨床』、守中高明、谷昌親、鈴木雅大訳、河出書房新社、2002年、p.153
[xxvii] 森田玲『日本の祭と神賑――京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち』、創元社、2015年、p.204。
[xxviii] 同書、p.204。
[xxix] 折口信夫『古代研究Ⅱ――祝詞の発生』、中公クラシックス、2003年、pp.108-109。
[xxx] 折口信夫『古代研究Ⅲ』――国文学の発生』、中公クラシックス、2003年、p34。
[xxxi] エドワード・ボンド『戦争戯曲集 三部作』、近藤弘幸訳、あっぷる出版社、2018年、pp.19-20。
[xxxii] 小田部胤久『西洋美学史』、東京大学出版会、pp.67-71。
[xxxiii] 小田部胤久『美学』、東京大学出版会、2020年、pp.360-361。
[xxxiv] 同書、pp361-362。
[xxxv] https://r3.responding.jp/r3-scape-city/